
愛犬が突然白い泡やネバネバしたものを吐いてしまったら、飼い主さんはとても不安になりますよね。
「一体何が原因なの?」「すぐに病院に連れて行った方がいいの?」と、頭の中が疑問でいっぱいになるでしょう。
特に初めて犬を飼う方にとっては、パニックになってしまうかもしれません。愛犬の様子をよく観察し、落ち着いてこの記事を読み進め、適切なケアをしてあげましょう。
犬が白い泡やネバネバを吐く…これって緊急事態?

愛犬が白い泡やネバネバを吐いた時、飼い主さんがまず気になるのは「すぐに病院へ連れて行くべき?」という点でしょう。
焦る気持ちはよく分かりますが、まずは落ち着いて愛犬の状態を観察することが重要です。すべての嘔吐が緊急事態を要するわけではありません。
約200件の症例を基にした獣医師の見解では、以下のポイントが緊急性の判断基準となります。慌てずこの基準を参考に、適切な行動をとりましょう。
重症化しやすい症状を見逃さないためにも、冷静に観察し、判断することが大切です。
緊急受診が必要なケース
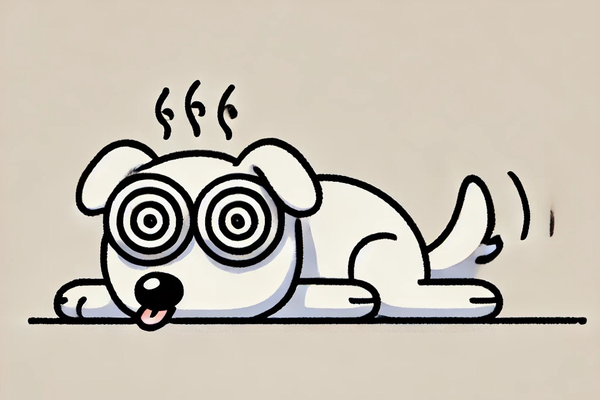
愛犬の様子がおかしい、何かいつもと違うと感じたら、ためらわずにすぐに動物病院へ連絡しましょう。
特に、嘔吐に加えて以下の症状が見られる場合は、一刻を争う事態の可能性があります。
迅速な対応が愛犬の命を守ることに繋がりますので、躊躇せずに、獣医師の指示を仰ぎましょう。
- 嘔吐を繰り返す、または吐きそうで吐けない様子
胃捻転などの危険な病気が隠れている可能性があります。胃捻転は大型犬に多く見られ、命に関わる危険な状態です。
- 意識がもうろうとしている、ぐったりしている
脱水症状や他の重篤な病気が考えられます。嘔吐によって体内の水分が失われ、脱水症状を引き起こすことがあります。
- 呼吸が荒い、チアノーゼ(舌や歯茎が紫色になる)
呼吸器系の問題やショック状態の可能性があります。チアノーゼは酸素不足のサインです。
- お腹が膨張している、痛みがある様子
胃拡張や腹膜炎などが疑われます。お腹が硬くなっていたり、触ると痛がる場合は要注意です。
- 痙攣を起こしている
神経系の異常や中毒症状の可能性があります。痙攣は様々な原因で起こりますが、いずれも緊急性を要します。
- 吐瀉物(としゃぶつ)に血が混じっている(鮮血またはコーヒーかすのような色)
消化管出血の可能性があり、緊急性を要します。鮮血は口や食道からの出血、コーヒーかすのような黒い血は胃や腸からの出血を示唆します。
様子見で良いケース
以下の場合は、比較的緊急性は低いと考えられます。ただし、あくまで目安であり、少しでも不安な場合は獣医師に相談することをお勧めします。
嘔吐が続く、他の症状が現れるなど、変化があればすぐに動物病院へ連絡しましょう。安易な自己判断は危険です。
様子を見る場合も、愛犬の状態を注意深く観察し、異変があればすぐに対応できるように準備しておきましょう。
- 嘔吐は一度だけで、その後は元気食欲もある
一時的な消化不良や胃の不調の可能性があります。過食や急に冷たい水を飲んだことなどが原因かもしれません。
- 吐瀉物(としゃぶつ)に血は混じっていない
消化管出血の可能性は低いため、少し様子を見ても良いでしょう。ただし、嘔吐が続く場合は注意が必要です。
- 食後すぐ、または空腹時に吐いた
早食い、空腹時の胃酸過多などが考えられます。食後すぐの嘔吐は、食べたものが消化されずに逆流している可能性があります。
空腹時の嘔吐は、胃酸が過剰に分泌され、胃粘膜を刺激していることが考えられます。
犬が白い泡やネバネバを吐く原因とは?

犬が白い泡やネバネバしたものを吐く原因は実に様々です。原因を特定することは、適切な治療やケアを行う上で非常に重要です。
以下に主な原因と、それぞれの具体的な症状、関連キーワードとの関係性について解説します。
約200件の症例データによると、最も多い原因は空腹時の胃酸過多、次いで食餌の変化、消化不良となっています。
これらの情報を知ることで、愛犬の嘔吐の原因を推測し、適切な対応をとることができるでしょう。
1. 空腹による胃酸過多(特に老犬で多い)
長時間何も食べていないと、胃に溜まった胃酸が粘膜を刺激し、白い泡状の嘔吐物を吐き出すことがあります。
これは胆汁が混ざっているため黄色っぽい色をしていることもあります。特に老犬は消化機能が低下しているため、空腹時間が長くなると胃酸過多になりやすい傾向があります。
「犬 吐く 白い泡 ネバネバ 老犬」で検索する飼い主さんも多いのではないでしょうか。愛犬が高齢の場合は、食事の回数や量を調整するなど、空腹時間を短くする工夫をしてみましょう。
2. 食後の嘔吐(食餌の変化、消化不良)
食後すぐに吐いてしまう場合は、食べたものが消化不良を起こしている、または新しいフードに急に切り替えたことによる胃腸への負担が考えられます。
「犬 吐く 白い泡 ネバネバ 食後」で検索する飼い主さんは、愛犬の消化器系の健康に不安を感じているのでしょう。
新しいフードを与える際は、1週間~10日ほどかけて徐々に切り替えるようにしましょう。また、一度にたくさんの量を与えず、少量ずつ何回かに分けて与えるのも効果的です。
3. 感染症(ウイルス性胃腸炎など)
ウイルスや細菌による感染症も嘔吐の原因となります。パルボウイルス感染症やジステンパーなど、命に関わる危険な感染症も存在します。
下痢や発熱を伴うことが多く、「犬 吐く 白い泡 ネバネバ 下痢」で検索するケースも少なくありません。感染症が疑われる場合は、他の犬との接触を避け、すぐに動物病院を受診しましょう。
4. 異物誤飲
おもちゃやビニール袋、布、靴下など、犬が食べてはいけないものを飲み込んでしまうと、消化器官に詰まり嘔吐を引き起こすことがあります。
吐瀉物に血が混じっている場合は、消化管が傷ついている可能性もあるため注意が必要です。
「犬 吐く 白い泡 ネバネバ 血」といったキーワードで検索する飼い主さんは、深刻な事態を懸念していると言えるでしょう。
異物誤飲が疑われる場合は、無理に吐かせようとせず、すぐに動物病院へ連れて行きましょう。
5. 慢性疾患(膵炎、炎症性腸疾患など)
膵炎や炎症性腸疾患などの慢性疾患も、嘔吐の原因となります。
継続的な嘔吐が見られる場合は、これらの疾患の可能性も考慮し、動物病院で検査を受けることが重要です。これらの疾患は早期発見・早期治療が大切です。
6. ストレスや環境の変化
引っ越しや新しい家族の加入、旅行、大きな音など、環境の変化によるストレスも嘔吐の引き金となることがあります。
犬は環境の変化に敏感な動物です。新しい環境に慣れるまで、優しく見守ってあげましょう。
家庭でできる対処法とケア
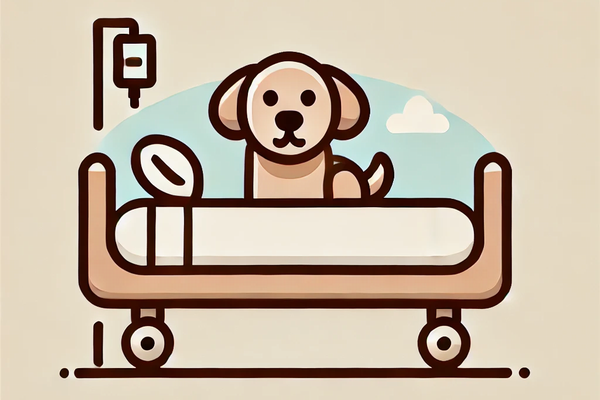
愛犬が白い泡やネバネバを吐いた際、緊急性が低いと判断した場合でも、適切なケアが必要です。ここで紹介する対処法は、あくまで応急処置です。
愛犬の状態が悪化したり、嘔吐が続く場合は、必ず動物病院を受診しましょう。
1. 水分補給
嘔吐すると体内の水分が失われるため、脱水症状を防ぐためにこまめな水分補給が大切です。少量ずつ水を与え、無理強いはしないようにしましょう。
冷たい水は胃を刺激する可能性があるため、常温の水かぬるま湯を与えましょう。
2. 食事を一時的に控える
嘔吐直後は胃腸が敏感になっているため、4~6時間ほど食事を控えます。その後、消化の良い食事を少量ずつ与え始めましょう。
鶏肉を茹でたものや白米、消化器サポート用のフードなどがおすすめです。脂肪分の多い食事や、香辛料の入った食事は避けましょう。
3. 安静を保つ
静かで落ち着ける環境を用意し、愛犬をゆっくり休ませましょう。ストレスも嘔吐の原因となるため、なるべく安静な環境を作ってあげることが大切です。
動物病院での治療
動物病院では、原因を特定するために様々な検査が行われます。血液検査、レントゲン検査、超音波検査などが一般的です。
原因に応じて、制吐剤の投与、点滴による水分補給、抗生物質の投与などの治療が行われます。獣医師の指示に従い、適切な治療を受けさせましょう。
嘔吐を予防するためにできること
愛犬の嘔吐を予防するために、日頃から以下の点に気を付けましょう。これらの予防策は、愛犬の健康維持にも繋がります。
1. 適切な食事管理
消化の良いフードを選び、早食いを防ぐ工夫をしましょう。早食い防止用の食器を使う、フードにお湯をかけふやかしてから与えるなど、様々な方法があります。
1日数回に分けて食事を与えることで、空腹時間を短縮し、胃酸過多を防ぐ効果も期待できます。
2. ストレス軽減
静かで落ち着ける環境を用意し、愛犬が安心して過ごせるように配慮しましょう。適度な運動や遊び、スキンシップもストレス軽減に効果的です。
3. 定期的な健康診断
年に1~2回の健康診断で、早期発見・早期治療に繋げましょう。健康診断では、獣医師に普段の生活や気になる点などを相談することもできます。
よくある質問(Q&A)
Q1. 子犬が白い泡を吐く場合はどうすれば良いですか?
子犬は消化器系が未発達なため、嘔吐しやすい傾向があります。
特に下痢や発熱を伴う場合は、すぐに動物病院へ連れて行きましょう。子犬の嘔吐は脱水症状を引き起こしやすいため、注意が必要です。
まとめ
愛犬が白い泡やネバネバを吐いた時は、落ち着いて状況を観察し、適切な対処をすることが大切です。
この記事で紹介した内容を参考に、愛犬の健康を守ってあげてください。少しでも心配なことがあれば、迷わず動物病院に相談しましょう。
愛犬と長く健康で楽しい日々を過ごすために、日頃から予防策を心掛け、異変に気づいたら早期に対応することが重要です。













